 |
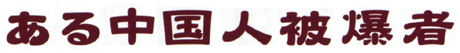 〜広島文理大卒業生 初慶芝女史を訪ねて〜 |
文・小林 文男
( KOBAYASHI, Fumio ) 広島大学名誉教授 |
ハルビンを発した列車が長春駅に着いた時、私の胸にこみあげてくるものがありました。それは、この地で六十年前、私の長兄が戦死したからです。二十二歳、陸軍士官でした。私は若くして逝った兄の最後を辿るつもりでした。 加えて、もう一つの大事な用件がありました。それは病床にあるという旧知の中国人女性を見舞うことでした。 初慶芝さんの被爆状況 その女性の名は初慶芝、現在八十五歳。広島大学の前身、広島文理科大学の卒業生で、在学中、原爆に遭った被爆者でした。あの日、彼女は卒業論文の準備のため鉄筋二階建の資料閲覧室にいたため命びろいしたのですが、骨折した上に大火傷を負い、救けを求めて火と瓦礫の市内をさまよい、そのあと一週間意識不明でした。彼女はこう語っています。 「恐ろしい地獄絵図でした。電車は焼け焦げ、車内の乗客は立ったまま、あるいは座ったまま、炭と化していました。見えるのは崩壊した建物と炎々たる烈火、聞こえるのはいつ果てるとも分からぬうめき声でした。」 これを語った時の彼女は比較的元気だったのですが、今回、三度目の出会いでは老いが目立ち、私の顔を見て微笑みベッドの上に身を起こしましたが、心臓病と神経痛を病み寝たきりの生活とのことでした。日本語もほとんど忘れており、懇談中、私のことを「森滝先生」と呼び、時々意識が混濁するようでした。 森滝先生とは故森滝市郎広島大学名誉教授のことで先生は彼女の恩師でした。 話は前後しますが、被爆の翌年、文理大史学科西洋史専攻を卒業した彼女は新中国誕生に歓喜し、一九五〇年勇躍帰国しました。 差別と苦難 しかし、憧れの祖国で彼女を待っていたのは被爆者であることからくるいわれなき差別であり、「敵国日本になぜ留学したのか」という周囲からの疑惑の眼差しでした。彼女は満州国派遣国費留学生だったのです。中国人にとって、日本の傀儡政権たる「満州国」に加担することは売国と屈辱の代名詞でした。彼女は私にこう話してくれたことがあります。 「帰国後、孤独な生活が続いた上に体の調子がとても悪かったのですが、原爆に遭ったこと、日本留学のことは誰にも隠していました。当時、私は被爆者と知られるくらいなら死ぬ方がましだと考えていました。」 彼女は結婚しましたが、一九五三年に出産した子供はすぐに死亡し、その後、子宮ガンにかかって手術を受け、それが原因で離婚しています。さらに、五十年代末の整風運動では「日本のスパイ」「階級の敵」のレッテルを張られ職場でも地域でも迫害され、文化大革命の時には農村で労働に従事させられました。 この生活は十年余りに及び一九七九年になってやっと職場への復帰が許されています。 使えない原爆手帳 初さんの辛酸を知った前記森滝先生が県の支援を得て彼女を広島に招き、原爆病院で治療を受けさせてくれたのは一九八六年六月のことで、彼女には広島市から原爆手帳が交付されました。 けれど、手帳は中国では使えません。彼女の病気治療の条件は現行法では「再来日」以外になく、日本に来なければ適切な処置は施されず医療手当の支給もありません。寝たきりの彼女の来日は不可能です。 「被爆者はどこに居ても被爆者である」との声が高まっています。けれども彼女のような存在に政治も法も冷たく、ヒロシマもまた無関心です。残り時間は多くはないのです。 別れしな彼女は何度も「母校の皆さんに宜しく」と言い、その目は潤んでいました。
|
広大フォーラム2004年12月号 目次に戻る
