 |
| 国立大学法人法が成立し、平成16年4月1日から、現在の国立大学は国立大学法人に移行することになりました。そこで、『広大フォーラム』では、本号と次号の特集テーマに法人化問題を取り上げることにしました。もっとも、現時点では細部について流動的で未確定な点もありますし、法人化後の広島大学については、現在「国立大学法人設立本部」(本部長:牟田学長)において、設立作業が急ピッチで進められているところです。そのため、本号では、法律が定めている国立大学法人の制度的枠組、いわば全国立大学に共通の部分の解説を主として扱っていますが、財務・会計制度、人事制度及び労働安全衛生法関係については、上記設立本部のそれぞれのワーキンググループの座長に、これまでの広島大学における議論にも触れつつ書いていただいています。各構成員が議論の前提となる基礎知識を共有し、「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」としての広島大学を構築するための議論が活性化することを望みます。 |
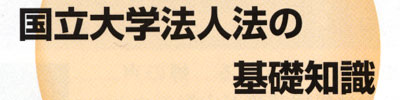 |
文・平野 敏彦 (HIRANO, Toshihiko) 広報委員会委員長 法学部教授 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国立大学法人法」(以下、「法人法」と略する。)は、平成十五年二月二十八日に内閣提出法案として衆議院に提出され、五月十六日に衆議院文部科学委員会審査終了・可決(法律の施行に当たって特段の配慮をすべきという十項目の附帯決議がなされています)、同二十二日に本会議審議終了・可決の後参議院に送付され、七月八日に参議院文教科学委員会審査終了・可決(二十三項目の附帯決議がなされています)、同九日に本会議審議終了・可決で成立し、七月十六日付けの官報で公布されました(法律番号は平成十五年法律第百十二号)。法人法の施行期日は十月一日とされ、国立大学法人設立の期日は平成十六年四月一日と定められています。 また、法人法公布と日を同じくして「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成十五年法律第百十七号)も公布され、この中で国立大学の現行の制度的枠組を定めていた「国立大学設置法」と「国立学校特別会計法」が廃止されるとともに、「学校教育法」や「教育公務員特例法」など五十二本の関係法律の一部改正が行われました。これらが一体となって、国立大学に法人格を付与することに加えて、予算配分方式や教職員の雇用形態の変更など、国立大学を取り巻く法的枠組が大きく変わることになります。
国立大学の法人化は、独立行政法人化(独法化)と呼ばれていた時期がありました。たとえば、広島大学において「国立大学法人設立本部」(九月三十日までは「国立大学法人設立準備会議」)の前身にあたる評議会の部会は、「独立行政法人化対策会議」(平成十三年四月設置。座長:生和元副学長、山西前副学長)という名称でした。 行政改革の一環として、一定の国の機関を切り離して独立した法人格を付与し、業務を運営させる独立行政法人を設立するための基本法として「独立行政法人通則法」(平成十一年法律第百三号。以下、「通則法」と略する。)が公布されたのは、奇しくも四年前の平成十一年七月十六日でした。独立行政法人はこの通則法と個別法(たとえば、「独立行政法人大学入試センター法」(平成十一年法律第百六十六号))に基づいて設立されます。 当初は、国立大学の法人化も通則法の下に実施しようと考えられていました。しかし、議論の過程で、特に、主務大臣による法人の長の任命(通則法第二十条第一項)や、主務大臣による中期目標の決定と独立行政法人への指示(同法第二十九条前段)などの点で、学問の自由(academic freedom)を享有し、大学の自治を保障されてきた大学については通則法の枠組は不適切だとの批判が、国立大学協会だけでなく、自由民主党政務調査会などからも出てきました。その結果、個別法とは異なる単行法を制定して法人化を実施することになり、学長の任免や目標設定について大学の特性・自主性に配慮した今回の法人法が制定されました。このことは、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学…における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」という国の配慮義務を定めた法人法第三条に反映しています。 通則法と法人法は、一般法と特別法の関係にあると言われることもありますが、この概念は特別法に規定がない場合は一般法の規定が適用されるという関係を指すときに使われるものですので、通則法と法人法の関係を指す場合には不適当です。通則法の数多くの規定が法人法に準用されているのは事実ですが(重要なものは以下で触れます)、法人法はけっして通則法の特別法ではありません。 以上のことから、国立大学の法人化を独法化と呼ぶのは概念の混同であり、避けるべきです。
現在の国立大学は、国立大学設置法第一条「(第一項)文部科学省に、国立学校を設置する。(第二項)国立学校は、文部科学大臣の所轄に属する。」という定めにより、国の行政組織の一部と位置づけられています。また、教員は教育公務員特例法第三条により「国立学校の学長、校長、教員及び部局長は国家公務員…としての身分を有する」とされています。このような文部科学省の内部組織である国立大学に、各大学ごとに法人格を付与することによって、国の組織から独立した「国立大学法人」を設立し、より自律的な運営ができるようにする制度的枠組を構築しようというのが、法人化の基本的発想です。 法人とは、自然人(生物としての人間)以外で、法律上の権利義務の主体として法律により認められた存在を指す法律用語で、一定目的のために結合した人的集団に法人格が付与された場合が社団法人、一定目的の下に結合されている財産の集団に法人格が付与された場合が財団法人です。法人格の付与という法的技術を用いることによって、構成員の変動にもかかわらず法的主体としての地位を継続させるという効果が生まれますが、いずれの集団にしても自然人のように目に見える存在ではありませんので、根拠法の定める手続によって設立し、登記により公示することが要求されます。また、実際に、法人の意思決定をし、法人の行為を執行するのは、自然人ですが、これを「機関」と呼びます。(機関には独任制のものと合議制のものがあります。) 日本語の法人という言葉は、ドイツ法の「Juristische Person」に由来しますが、英語で法人にあたるのは「corporation」という言葉です。その語源は、体(body)を意味するラテン語の「corpus」です。法人の機関を指すのに、英語では器官・臓器を意味する「organ」を用いますが、興味深いことです。法人化は「incorporate」となりますが、アメリカの会社名の後ろに付けられている「Inc.」が「incorporated」(法人格を付与された)を表しています。なお、国立大学法人は、文部科学省の英訳によると、「National University Corporation」となり、独立行政法人の「Independent Administrative Institution(=IAI)」または「Independent Administrative Agency(=IAA)」(業務内容によって使い分けられています)とはまったく別の表現となっています。 法人に関する一般法は民法ですが、たとえば、商法による株式会社(営利法人)、私立学校法による学校法人、医療法による医療法人など、個別の法律に基づいていろいろな種類の法人が設立されています。国立大学法人は、国立大学法人法に基づく法人です。国立大学が一個の独立した人格を持つ存在になったということは、後見人としての文部科学省の役割を無視できないとしても、権利・意思・行為の主体であるとともに、義務・責任の帰属主体となったということです。
法人法等の成立により国立大学に適用される法律は一変したわけですが、まず最初に、法人法成立までの経緯を簡単に振り返っておきましょう。 法人化自体は、中央教育審議会答申(昭和四十六年)や臨時教育審議会答申(昭和六十二年)でも言及されていましたが、現実の課題となってきたのは、平成九年の行政改革会議最終報告で「独立行政法人化は、大学改革方策の一つの選択肢となり得る可能性を有している」と指摘されたことに始まります。平成十一年の小渕内閣時に国家公務員の二十五%削減が閣議決定され、「国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として検討し、平成十五年までに結論を得る」ということになりました。 その後、国立大学協会での議論や自民党政務調査会の提言などを踏まえて、平成十二年七月には文部科学省に「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」が設けられました。また、平成十三年六月に経済財政諮問会議で発表された「大学(国立大学)の構造改革の方針」(いわゆる遠山プラン)では、国立大学法人に早期移行すべきことが強い調子で述べられていました。平成十四年三月の調査検討会議の最終報告を受けた後、同年六月には、「文部科学省は、国立大学の法人化と教員・事務職員等の非公務員化を平成十六年を目途に開始する」との閣議決定を経て、平成十五年二月に国立大学法人法案等関係六法案が国会に提出され、冒頭で述べたように七月に成立したわけです。
法人法のねらいは、次の五点にまとめることができます。 1.大学ごとに法人化し、自律的な運営を確保すること 2.民間的発想のマネジメント手法を導入すること 3.学外者の参画による運営システムを制度化すること 4.非公務員型による弾力的な人事システムに移行すること 5.第三者評価の導入による事後チェック方式に移行すること
法人化された国立大学は、現行制度に比べ各大学の運営の自由度が大幅に増すと言われていますが、その自由をコントロールするために導入されたのが、いわゆる目標達成方式という考え方です。つまり、各大学ごとに策定された理念・目標・計画に基づいて運営され、事後にその目標達成度が第三者機関に評価され、その結果が大学への資源配分(運営費交付金の額など)に反映されるというサイクルです。評価機関としては、文部科学省に「国立大学法人評価委員会」が設置されることになっています。 この運営方針は〈表1〉に示すように、三段階に分けて策定されます。すなわち、第一段階は六年間に達成すべき「中期目標」で、文部科学大臣が定めますが、国立大学法人の意見に配慮するものとされています。この意見がいわゆる中期目標の原案になります。(独立行政法人では、中期目標は主務大臣から一方的に指示されるものですので、この点が大きく異なります。)第二段階はそれを達成するための「中期計画」で、国立大学法人が作成し、文部科学大臣の認可を受けます。第三段階は、事業年度(四月一日~三月三十一日)ごとに法人が作成する「年度計画」です。年度計画については法人法に規定がなく、通則法第三十一条が準用されています。 法人化後は業務内容について大幅な自由化が行われますが、〈表1〉からもわかるように、運営に関しては、かなりの程度、文部科学大臣の関与があります。また、国立大学とその附属学校の授業料その他の費用に関しては、文部科学省令で定めることになっています(第二十二条第四項)。 <表1> 中期目標・中期計画・年度計画の対比
国立大学法人は、国立大学を設置することを目的として設立される法人です(第二条第一項)。つまり、国立大学法人広島大学が国立大学広島大学を経営しているということです。わかりにくければ、学校法人○○学園が私立の○○大学を、医療法人○○会が○○病院を経営しているのと同じ関係だと考えてください。国立大学法人と国立大学の違いは、後述するように、経営協議会の審議対象が「国立大学法人の経営に関する重要事項」(第二十条)、教育研究評議会の審議対象が「国立大学の教育研究に関する重要事項」(第二十一条)という規定に端的に表れています。一般に経営と教学の分離と言われている所以です。 この国立大学法人を代表し、法人の業務を総理するのが「学長」です。学長は、国立大学法人の長であると同時に、学校教育法第五十八条第三項に規定されている大学の「校務をつかさどり、所属職員を統督する」職務、つまり現在の学長の職務も兼ねるポストとして位置づけられています(第十一条第一項)。一部の私立大学にあるように、経営の責任者たる理事長と教育研究の責任者たる学長を一人が兼ねている形です。任期は二年以上六年を超えない範囲内で、法人の規則で定めることになっています。学長の任免については、後述します。 法人の「役員」には、学長のほかに、監事が二人と一定数の理事がいます。(理事の員数は、法人法別表第一の第四欄で、各大学の規模に応じて上限が定められており、広島大学は七人となっています。)「監事」の職務は、法人の業務を監査することで、監査の結果に基づき、必要なときは、学長または文部科学大臣に意見を提出することができます(第十一条第四、五項)。任期は二年と法定されており(第十五条第三項)、任命権者は文部科学大臣です(第十二条第八項)。「理事」の職務は、学長を補佐して法人の業務を掌理することです。また、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行うことになっています(第十一条第三項)。理事の任命権は学長が握っており、任期も自分の任期内であれば自由に定めることができ、解任権もあります。(理事の任命・解任は文部科学大臣への届出事項であるとともに、公表義務があります。)株式会社で言えば、監事は監査役、理事は取締役、つまり業務担当重役のようなものです。(理事に副学長の肩書きを与えるかどうかは、各国立大学法人が決めることです。)なお、理事と監事のいずれにも、「現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者」、いわゆる学外者(非常勤も可)を必ず含むように人選をしなければなりません(第十四条)。 「役員会」とは、学長が重要事項(第十一条第二項。〈表2〉参照)を決定する際に必ず事前に「議を経なければならない」とされている機関で、学長と理事から構成される会議体です。(監事はメンバーではありません。)もっとも、「議による」との文言が用いられていないので、役員会は議決機関ではなく、審議機関にすぎず、その審議結果が学長を拘束するものではありません。だから、役員会は最高意思決定機関ではないのですが、役員会の審議結果と異なる決定を学長が行う場合には、十分な説明責任義務が学長に課されていると考えるべきでしょう。ここに、学長は単なる執行機関ではなく、すべての権限と責任を一身に担うものだとする法人法の精神、つまり学長のリーダーシップの重視が明確に表れているところです。 <表2> 役員会の議を経なければならない重要事項(第11条第2項)
現在の国立大学では、各部局長と部局選出の評議員等から構成される「評議会」で大学の運営がなされています。法人法ではここが大きく変わります。 国立大学法人には、重要事項を審議する機関が、内容に応じて二つ、国立大学法人の経営面を審議する「経営協議会」と国立大学の教育研究面を審議する「教育研究評議会」が設置されます。経営協議会委員は、学長、学長指名理事・職員、学長任命学外者(教育研究評議会の意見を聴いたうえで任命)から成り、このうち委員総数の半分以上が学外者であることが要求されます。一方、教育研究評議会評議員は、学長、学長指名理事、部局長等(教育研究評議会が定めた者に限る)、学長指名職員から成りますので、学内者だけから構成されています。これらの審議機関の扱う内容は、これまでは、国立大学設置法第七条の三を根拠に、評議会が扱ってきました。三者を比較すると、〈表3〉のようになります。 <表3> 法人化後の審議機関と現行の評議会の比較
学長の任免の説明には、以上の二つの審議機関の説明が前提となります。というのは、学長を任命または解任する権限は、文部科学大臣がもっており、その任免の際には国立大学法人の申出に基づくこととされています。その申出を行うのが「学長選考会議」で、二つの審議機関から選出された同数の委員をもって構成される常設の機関です。そのうち、経営協議会選出委員は学外者に限ると定められており、教育研究評議会選出委員は当然学内者ですので、結局のところ、同数の学外者と学内者で構成する会議体で、学長を選考するという制度設計になっているのです。(ただし、委員の三分の一を超えない範囲で学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができます。) 学長の選考は、この学長選考会議が、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者」のうちから行うことになります。(なお、理事にも学長と同じ属性が要求されています(第十三条第一項)。) 学長の採用のための選考は、これまでは、教育公務員特例法第四条を根拠にして、評議会が、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者」について、評議会の議に基づき学長の定める基準で行ってきました。広島大学の場合は「広島大学長選考規程」により、評議会が選挙管理委員会をその都度組織して、学長又は専任の教授、助教授、講師若しくは助手に選挙資格を認めて、学長選挙を実施してきました。この長年の親しまれてきた制度は完全になくなってしまいます。
法人法は、研究科や学部などにはほとんど触れていません。これまで、研究科・学部・学科等が政令事項や省令事項であった点を考えれば、大きな変更です。法人法には、教授会という言葉は一度も出てきませんし、教員も二度しか出てきません。 これまで教授会について定めていた国立大学設置法が廃止され、教育公務員特例法も改正され、国立大学は同法の適用外となりました。しかし、学校教育法第五十九条「(第一項)大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。(第二項)教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。」は改正されていないため、教授会そのものは法人化後も存続します。しかし、法令上の位置づけが大きく変わり、各大学の内部規則に大幅に委ねられたので、大学ごとにそれぞれ様々な形態で運営されることになるでしょう。
法人法には、財務・会計についての規定は第三十二条から第三十四条までの三条のみ、人事管理についてはまったく規定がありません。それを埋め合わせるために、通則法の規定を、財務・会計については十五条(通則法第三十六条から第五十条まで)、人事管理については四条(第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条)を準用しています。人事面での学長権限も拡大され、すべての「職員」(教員も含む)は学長が任命することになります(通則法第二十六条準用)。さらに、非公務員型の雇用形態に移行するため、雇用関係や労働条件等については一般の労働法がそのまま適用されます。これらの点については、「法人化後の財務・会計制度について」(国立大学法人設立本部財務・会計制度WG座長・阪口経済学部教授執筆)と「法人化後の人事制度について」(同人事制度WG座長・辻法学部教授執筆)を掲載していますので、参照して下さい。
法人法は、全体が四十一条から成る比較的小さな法律ですが、実際には、全部で四十条にわたって、通則法を準用しています(第三十五条)。「準用」という法令用語は、ある事項に関する規定を、他の類似の事項について、必要な修正を加えてあてはめるという法令作成技術で、これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。すなわち、「Aの場合には(法律要件)、Bせよ(法律効果)」という条文を、’Aの場合に準用すれば、「’Aの場合には、Bせよ」という条文があるものと扱ってよいということになります。たとえば、通則法で「独立行政法人は、~」という条文を準用した場合、「国立大学法人は、~」という条文があることになり、「~」の部分は共通になるので、両者の取り扱い方が同じになるのです。だから、法律の全体像をつかむためには準用されている条文を併せて読まなければならず、法律に慣れていない人には評判の悪い法令作成技術です。置き換える語句がわかりにくい場合は読替え規定が定められることもあり、法人法第三十五条では表形式で与えられています。
以上説明したことは、法人法がすべての国立大学法人に従うべきことを要求している枠組です。各法人は、この枠組の中で、創意・工夫をこらし、個性が輝くような細部の制度設計を独自にしていかなければなりません。学長のリーダーシップを強化するという方向性は、平成三年の大学設置基準大綱化以降の基本的な流れでした。しかし、ボトムアップ型という言葉で表現されることの多い従来の大学流の意思決定方式が、機動的・戦略的で迅速な意思決定の制約となる場合もなきにしもあらずというのが実情でした。その制度的前提が、法人化で大きく変わります。いわゆるトップダウン型の意思決定が行いやすくなったのです。 権限の一極集中は、一般的に言って、一部を利するための権限濫用や専断的決定につながるおそれが高いものですから、コントロールが必要です。これまでの大学運営については、学内構成員による民主的決定こそがコントロール方法として最善だと考えられてきました。法人化後は、文部科学省、各種の評価機構、運営に参画する学外者、文部科学大臣任命の監事などによるコントロールの仕組みが法定されています。その一方で、学内構成員である教職員が大学の意思決定にどの程度、またどのように参画できるか、また決定に対する異議申立てルールをどのように設けるかは、各大学法人の決定に委ねられています。現代の世の中をおおう効率性という価値以外の価値に配慮するというのが、大学の特性というものではないでしょうか。そう考えると、意思決定の公正さやそのプロセスの透明性、事前事後の説明責任などは、考えておくべきポイントになるでしょう。 法人化という大波、いや津波がやってきたため、大学の変化はなんでもかんでも法人化の結果だととらえられかねません。しかし、法人法が成立したためにやらざるを得ない法定されている部分と、その枠内で各国立大学法人の自主的判断に任されていて、どうにでもできるのだけれども、我々はあえてこうするのだ、あるいはこうしたいのだという部分が混同されてはなりません。独自の運用で対処していくとしても、学内構成員を納得させるに足る一定のルール化は必要でしょう。その場合、将来を見通す大学人の見識こそが問われるのです。その前提として、法人法の核心部分をしっかりと把握しておいてください。 今は法人化の前夜です。あと半年すれば、未知の大海に出帆しなければなりません。嵐を乗り切れるだけの装備を充実しておくことが、この時期に広島大学の構成員である我々の責務です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||